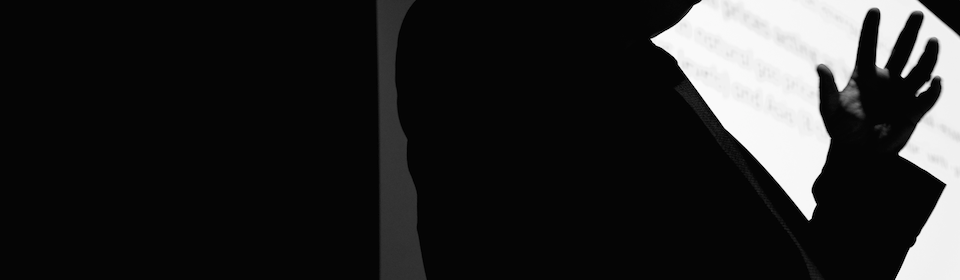不安定な「知」を楽しむ
東京大学大学院農学生命科学研究科教授(2015年3月まで在職) 黒倉壽

———黒倉先生は養殖の専門的な研究から始められて、今は海洋政策や経済評価、心理学的な話など幅広く活動されていますが、研究の経歴を教えていただけますか?
黒倉:私は大学院の時に魚の精子の保存法をやってて、極めてテクニカルなものや細胞の話をしていました。その路線で行っていれば、細胞をそのまま扱うようなことをやっていたはずなのです。
私は東大紛争があって入試がなかったときに高校を卒業した学年です。だから、その1年後に東大に入っているのです。そうすると少し時代の雰囲気が分かると思うのだけれど、連合赤軍の事件があったりして、大学へ入った時には大学が殆ど正常化していないから授業は殆どなくて、あまり勉強をしていないのです。そういう中でいろんな人が、いろんなかたちの生き方をしていました。当時、大学院を飛び出していった連中が日本で開発コンサルみたいなものがボコボコとつくっていたのです。私もその人たちの仲間に入って給料はあまりないけれども、やがてくるであろう時代を予測して、やってみることにしました。当時、日本の水産技術というのは結構使えて、先端性があったんです。現場にも根ざしていたから技術移転というかたちでコンサルティングできました。ところが、やがて南南協力みたいなものが主流になってきて、うまくいかなくなってきた。例えば、アフリカでティラピアの養殖技術を普及するときに技術屋として誰を連れて行くかと言ったら、フィリピン人とかを連れて行ったほうが日本人よりはるかにいいですからね。それで開発というのは極めてソフトな部分、つまり全体のプランニングとかに移っていくだろうと、漠然と予感したのです。
当時、水産の中で東大系のコンサルタント会社というのはうち1社しかなくて。最初は市ヶ谷のアパートの一室で5~6人が寄り集まって手探りでやってる会社でした。水産屋だけど自分の持っているサイエンスは全く使えない。むしろ、そこでは経済屋からいろんな情報を持ってきたり、交通システムの人、建築の人、もっとハードなところだとエンジン、機械とか、そういう連中と付き合わざるを得なくて。結局、コンサルティングあるいはエンジニアがすべきは、いろんな情報を集めて取りあえずソリューションをつくることで、それがエンジニアとしてやらなきゃいけない仕事で、そこにお金を払ってくれるのだということに気付くんですね。それまではサイエンスしか知らなかったので。幾らお金と時間をかけても真実を追究するのだというスタイルが大学の中ではいいのだけれど、実際の産業はそうはなっていないということを覚えたわけです。
その後、事情があってその会社を辞めて大学の研究者に戻ったのですが、そのときに社長と約束をして、おまえが辞めるということ自体に関しては反対しないけれど、ずっと一緒に付き合おう。おまえが大学に戻るということは、うちの会社としてもプラスだと考えていると。それはなぜかというと、いろんな情報源が必要だからですよね。コミュニケーション能力というか、どのぐらい人脈を持っているかということがコンサルとしての勝負だから、おまえが大学に戻って人脈を広げてくれるのだったら会社としてはプラスになるから、まあ頑張れよ、ということで送り出してくれて。結局、一生その会社とは付き合うことになりました。一昨日もその会社から電話かかってきたかな(笑)こんな感じに元々いたサイエンスの世界に戻ってきたときには、すでにエンジニアリングというものがあるのだとは知っていたわけです。

サイエンスとエンジニアリング、両方を知るからこそ分かる
それで、東大で農学国際専攻といういわゆる課題志向的で、最初からブロードに(幅広く)ものを学生に教えるような専攻をつくるときに来ないかと言われて。多分、私を呼んだ人は、私がそういう経験があるということは知っていたのでしょうね。
農学国際でやっているときに、何年かたってJABEE(技術者教育認定機構)の初代の農学系審査委員長になりました。そのときのJABEEはエンジニアリング重視でサイエンスに対してはやや否定的でした。教育というのはソリューション・オリエンテッド(解決志向型)でやらなければ役に立つ人はつくれないという考え方ですね。でも、私はそれは違うだろうと思っていたんです。エンジニアリングもあるけれど、でもサイエンスというのがやっぱりあるんだと。サイエンスを知っているからエンジニアリングもできるし、エンジニアリングを知っているからサイエンスを考えられるみたいな関係をつくっていくことのほうが、はるかに大事だというふうに思っていました。
だから、必ずしもソリューション・オリエンテッドに、あるいは最初からブロードに教えたほうがいいとか悪いとか、そういう問題ではないだろうと思っているのです。ただ、そういうことを知っている人間が多くなるということはいいことだろうというふうに思っているのです。それが今、私がこういうことをやっている最大の理由です。
社会が失った機能を大学が担う
———民間に1回出られて、そこでの経験が役に立つというお話ですが、先生はご自身のブログで学生時代に1回社会に出たほうがいいと書かれていましたね。
黒倉:確かに社会に出たほうがいいのかもしれないと、私は思います。ただ、大きな流れを見てみると大学の中でそういう課題志向的なもの、あるいはプロブレム・ベースド・ラーニング(PBL)みたいなのが強調されたり、アクティブラーニング、自ら勉強して広いネットワークで自ら知識をつくっていくみたいな話が出てくるのを聞いていると、ちょっと違和感があるのです。つまり、もともとそういう機能は社会が持っていたはずだと。今更、大学にそれを要求するということは、社会がそういう能力とシステムを失ったんじゃないかと思うのです。とすると、どこかが補完しなきゃいけないのだろうとは思います。それが大学なのか、社会がそういう能力を取り戻すべきなのかは分からないです。結局、社会がそういう機能をしっかり持っているのだったら別に大学にやる必要はない。だけど、社会に既にないのだとすれば、大学は新たに何かつくらなきゃいけないかもしれないと思います。

———先生は最初専門特化した現場で博士も取られていますが、GSDMのように専門的なものをやりながら同時に政策を学ぶという教育モデルをどうお考えですか?
黒倉:現段階は、まず今は実験段階なのだと思います。教育というのは、うまくいく時とまずくいく時があるもので、それが教えられる側の多様性みたいなのに関係していて、ある人間にはある教え方が適しているけれど、他の人間にはその教え方は全然適さないということがありますよね。知識というのは、その人間のものの覚え方とか関心ということをうまく捉えてやらないと、やっぱり難しいと思うのです。そこはやっぱりプロフェッショナルな教育技術が要るのだろうと思います。ただ、一つだけ言えるのは、もしそういうものを自立的に学生が学ぶのだとすれば、自律的に学べるだけの基礎力というか体力と言ったらいいのか。つまり、ものすごい猛練習すればいい選手になるけれど、そのためには猛練習ができる体力が必要なのです。それをどこかでつくらないと難しいと思います。
農学国際の経験から言うと、例えば僕自身の経験と照らし合わせても分かるのだけれど、やっぱり大変だったのです。というのは、水産屋が建築の人と話をしなきゃいけない、水産屋が経済屋さんと話をしなきゃいけないというときに、全く違う枠組みの中で相手は話をする場合に、その相手の言葉が理解できなきゃいけないですよね。すると、その相手の言葉が理解できるだけの言葉の力というのか、国語力に近いものだけれど、相手が言っていることの論理構造がこうであって自分とどういう立場が違っていて、自分の論理構造とはこう違うのだけれど、相手はそれなりに構造を持った話をしているのだということが分かること。それはやっぱり必要だと思います。
———最近の学生は忙しくて大学院生の間にそのようなことを考える心の余裕がないという話を聴くのですけれど、実際にそんなイメージを持たれています?
黒倉:何と言ったらいいかな。今の学生が能力的に優れていないとか、今の学生が持っている関心方向が間違っているとか、そう言う気はありません。ただ、そうじゃなくて短距離を走るときと長距離を走るときは能力が違うし、走り方が違いますよね。やっぱり今の学生のほうが「よーい、ドン」で問題を解かせたときに早く解くと思いますよ。解法もきちっと整理されて頭の中に入っているし、それだけの競争にやっぱり耐えてきているからだと思います。
僕らが高校の頃の数学の解き方とか、ああいうのとは違っているような気がしますよね。僕らはもっと気の利かない解き方をしていたと思います。だから間違えたり、ゴールできなかったりすることが多かった。ただ、そういう中で解けない問題があるのだけれど、そういうものと解けないなりに付き合うと言ったらいいのかな。つまり、分からないことを何時間でも考えていられる思考のスタミナみたいなものが少し違ってきているのだろうなという。つまり、昔の人ってどうでもいいことをずっと延々考えていますよね。(笑)
———今の学生に期待することや、このような経験をしてほしいと思うことはありますか?
黒倉:昔はなぜだろう、昔の若者はある意味無鉄砲だったのか分からないけれど、そんなに将来を予見していなかったですよね。私がいつも反対していることがあって、学生に実験でも研究でも、何かを教えるときに仮説を作って、仮説検証的にそれを詰めていくことが科学なのだと教えるのだけれど、それって一番科学の中で面白くない部分を教えていると思うのです。それは面白くないし、楽しめないだろうと。科学、生物だって他にもっと面白いものがあって、もっと面白い発見があって、そのことに心を動かしていくというほうがはるかに科学の魅力で、それに委ねて生きていくというのが一つの生き方だろうという気がして。何か思い描けるものが、あらかじめストーリーがあって、それを検証していけばいいというのは、実に痩せた科学観みたいな気がします。

「知」とは不安定に流されて漂っているもの
黒倉:この前ここで初等の海洋教育サミットをやっているときに、逗子開成中学がやっていたことが面白くて。それはヨットを自作させることと遠泳なのです、中学生だからもちろん泳ぎの得意な子も下手な子もいるのだけれど、全員にさせるという話で。体育の授業としてそれはやっているだろうし、あるいはヨットを作ることの技術家庭としてやっているのだと思うのだけれど。僕は遠泳は好きなのです。「年寄りの冷や水」でやめろと言われるのだけれど、海岸に行くと泳ぐと、どこか向こうに島があるとそこまで泳いで行きたいなと思うほうなのです。実際やってみて怒られたりするのだけど、何で好きなのかというとあの不安定で流される感じが好きなのです。つまり、こうやって泳いでいるけれど実際に流れが出てきて自分は流されているよなと。あの島には着けないかもしれないなとパニックが起こりそうになるのだけれど、それをいや、待て、待て、パニックを起こしちゃいけない、やっぱりじわじわと寄っていけばいいんだと思って。そういう不安定な自分みたいなものをコントロールするというのが面白いと思うのです。
そういうふうに世界と向き合うという感覚が、私に言わせればそれって知性だと思うのです。つまり全てを読んで読み切って、それに合わせて行動することが知的なことだというのはものすごく知の一部分しか見ていなくて、向こう側に闇のようなカオスというか暗闇があってそれと対峙しているという感覚。それに対して自分の内的社会をどういうふうに動かせばいいかと考えるほうが、僕は知的作業だと思うのだけれど。やっぱり知というのは不安定に流されてただよっているものだと思うのです。
皮膚感覚として、知的に不安定で、流されてみるということをどのぐらい経験させるか。だから教育の中で非常に安定的に鮮やかに説明してみせること、それが知性なのだという。でも、それでは届かないサムシングがあって、それに向かってどう自分が対峙するかという。そういうことを、かなり早い時期に皮膚感覚として教えるということは重要だと思います。

———それをどう体系的にやっていくかというと、やや泥臭い感じの勉強などにならざるを得ないのでは?
黒倉:そうかもしれないですね。その辺で若い人たちに何か言うことがあるとすれば、僕らがその一つ前のかなり決定論的なものの中で生きてきて、それが知性だと思って育ってきちゃったから、ある意味これ以上弾力が利かないところがある。ただ、僕は幸いに社会との接点があったので、それだけでは解けない問題があるとなんとなく直感的に思っていたわけです。だから学としてそれをやるのであれば、今の若い人はその感覚を大事にして新しい方法論なり、新しい分野みたいなものをつくっていったらいいんじゃないかと思いますけれど。それは恐らく、ひょっとすると経済学にも収まらないかもしれないし、生態学にも収まらないかもしれないし、あるいは生理学みたいなものも入ってくるのかもしれないし。だから極めて不思議な、僕らがサイエンスだと思っていないようなものが育ってくるのだろうと思っていますけれどね。
GSDMサマープログラムについて
———黒倉先生は復興のことにいろいろと関わっておられますが、GSDMでは去年のサマープログラムを東北で実施しましたよね。
黒倉: はい、やりましたね、サマーセミナー。被災地の人には悪いのだけれど、これは具体的に何かを考える材料としては悪くない材料だと思います。セミナーというイベント的なものではあるけれど、その中でかなり真剣に力を出して考えなきゃいけないテーマじゃないですか。そういうテーマの真剣さみたいなものが前提にあるわけです。
僕はそれまでも随分サマースクール的なものは経験があって、その経験から日本人の比率が多数派ではいけない、それでは効果が上がらないということは知っていたんです。もう一つは、1つのグループを大きくしてはいけないということも知っていた。だから4人で日本人1人という構成にしました。6人を超えるとやらなくてもいい人が出てきちゃう。やらなくてもものが動いちゃうと、どうコントリビュートしたらいいかということを考えない。だからグループワークをやらせるなら、できるだけ小さなグループをつくるというのが一つのセオリーだと思います。
あの状況下で、4人グループの中で自分1人だけが日本人だという状況をつくると、結局インタビューをするにしても何かを相手に求めるにしても、自分がある役割を果たさないと前へはいかないのだと感じるわけです。それは英語がうまいとか下手とは全く関係ないところで、自分がなんとかコントリビュートしなければいけないと。そういう状況に1週間なり何なり自分を置いてみるというのが、トレーニングとしてはいいと思います。
———確かにそうですね。サマーセミナーには外国人も多いですが会話は英語ですか?
黒倉:ええ、サマーセミナーの場合は外国の学生が多いから基本ディスカッションは全部英語でやらなきゃいけないですね。でも参加した学生も最初はやっぱり自分は英語が苦手だと言うんです。日本人は大体、皆そうなのですけれど、参加した学生が全て英語が得意だったわけではないですよ。でも、最後の最後にくると、もう言葉がうまいかどうかなんて関係ないのですよね。何しろコミュニケートできる、その場で直に情報を取ってくる人間は自分しかいないので、取ってきた情報を仲間に、つたない英語でも何でも、何が何でも伝えなきゃいけないわけですよね。
英語のコミュニケーションの壁があったけど、気がついてみると乗り越えていたみたいな、そういう効果があるだろうということは期待しました。
———実際にはどうでしたか?
黒倉:実際に効果はあったと思いますよ。

戦後と現在、「復興」という重なり合い
———震災後に東北の漁業とか沿岸部に先生が関わられたのは、以前、大槌におられたという経験が関係しているのですか?
黒倉:卒論や修論のときに大槌に行っていたことは確かで、学位論文のときも大槌で採ったデータを使っているから大槌とは縁があるのです。だけどあの復興のときに何で私が呼ばれたのかというのは、実はよく分からないです。ただ、声が掛かったときに「エッ、大槌?」という感じはなかったです。ああ、あの大槌ですかというような感じだったので、昔大槌に行っていたということが全然関係ないわけではないと思います。
大槌の復興をやっているときに一つだけ思い出したことがあって。復興という重なり合いで。それは戦後復興というか、私は1950年生まれだから、あの頃の人たちはどう生きていたのだろうと。子供の頃は自分が町工場の生まれだということに関して、中小企業的なものに政策が必ずしも厚くないということに対して若干の不満はあった。しかし、そう生きるものなのだというふうに思っていたのですね。つまり、要するに事業なんていうものは潰れちゃうし、おやじもよく言っていたけれど、うっかりすれば事業なんていうものは潰れちゃうんだ、そういうふうにできているんだよ、それでいいんだというふうな言い方をしていて。しかし、じゃあそれは悲惨だったかというと、結構突き抜けた明るさがあって、毎日楽しかった。毎日楽しかったことの原因って一体何だろうと思うと、結局、自分と何かと向き合っている感じですよね。一生懸命パーコレーターを作ったりして。そのパーコレーターは今でも研究室で使ってますよ。
パーコレーターはまだいいほうで、この前実家で見つけたおやじの手紙に出てたのは、何だかよく分からないアルミのお皿を進駐軍に納めるという話でね。納期が遅れた言い訳を適当にごまかして、英文のタイプライターで大学も出ていない男が一生懸命タイプを打っているのです。それって何なのだろうと。それは大変悲惨なことなのか、面白いことなのかということですよね。
それで思ったのは、結局あの当時のああいう連中というのは、きっとどこかで面白がってやっていたのだと思うのです。それは失敗したら大損するのだから大変と言えば大変かもしれないけれど、だけど持っている雰囲気はそんなに暗くなかった。結局、あれを面白がってやっているおやじというのは日本中にごろごろいたのでしょう、きっと。そういう中に、例えばソニーだったりホンダだったりというのがあって、それがたまたま成功したのだと。1,000人いたとすれば999人は物にならずにそのままいったのだと思うけれど、それはそれでいいじゃないという気がするわけ。だって、楽しんだのだから。だからそれと今を比べたときに、そういうことでポジティブに生きていく人間がどのぐらいできてくるかということが復興の焦点だと思うのです。高度成長期とか震災復興、そういうものをつくっていったのはあの面白がってそういうことをやっているおやじたちで、それが物事の本質なのだろうと、パーコレーターとおやじの手紙が出てきたときに思ったのですよね。
(インタビュー 岸本充生、記事構成 柴田祐子)
※参考リンク
- 東京大学大学院農学生命科学研究科農学国際専攻
http://www.ga.a.u-tokyo.ac.jp/ - 日本技術者教育認定機構(JABEE)
http://www.jabee.org/ - 全国海洋教育サミット
http://rcme.oa.u-tokyo.ac.jp/events/post847.html - 黒倉壽先生ブログ
http://www.future-fisheries.jp/