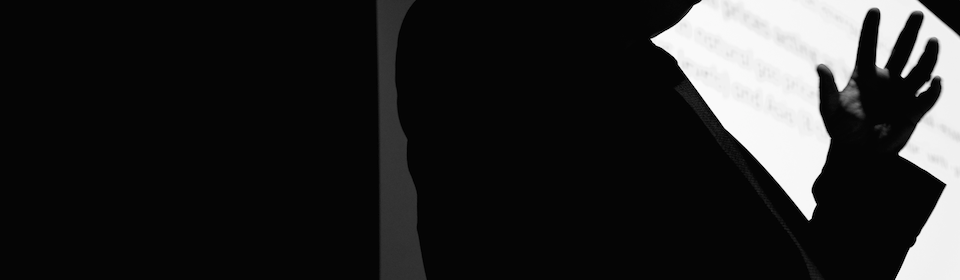国際舞台で仕事をするために 必要と思われることを伝えていきたい
東京大学政策ビジョン研究センター教授 芳川恒志

———芳川先生は現在ミャンマーの地方電化のプロジェクトに携わられるなどグローバルにご活躍ですが、今に至るまでの経緯やきっかけなどを教えてください。
芳川:私は広島の高校から東大法学部を出て当時の通商産業省に入りました。1981年、最初に配属されたのが資源エネルギー庁原子力産業課で、発電以外の核燃料サイクルを担当するところでした。核燃料サイクルに関して国際的なことも担当する課だったのですが、そこで行政官としての基礎、箸の上げ下げをたたき込まれました。国内の行政を行なううえでも常に国際的な動向に注意しておくことが大切だと学んだことが思い出されます。その後入省5年目にアメリカで2年間留学する機会がありましたが、勉強に加え他国の行政官や国際機関の職員はじめインターナショナルな人たちとも知り合いになり社会人としての視野が広がりました。最初の年に学んだケネディ・スクールでは1年間の修士プログラムでしたので、翌年できたばかりのUCサンディエゴのIR/PS(Graduate School of International Relations and Pacific Studies、現School of Global Policy and Strategy)という太平洋に焦点を当てた大学院に移り、そこでvisiting scholarとして1年間在籍しました。学生でないいわば自由な立場で知的活動に接してさらに自分のフロンティアが広がったように思います。さらに、留学から帰国後役所の人事ローテーションで多くの海外での勤務を経験させてもらいました。留学直後に霞ヶ関で2年間仕事をした後、通産省から外務省に出向して在テヘラン日本大使館の経済担当書記官として3年間赴任しました。1990年から93年、第1次湾岸危機のときです。イラン自体は紛争の当事国ではなかったのですが、それでもイラクとの間にイラン・イラク戦争の捕虜の交換がおこなわれていて、イラクとクェートの隣国であるイランで勤務し本当に貴重な経験をしました。1998年から2001年にはニューヨークのJETROに3年間貿易保険の仕事を、その後ジュネーブの日本政府代表部でWTOのドーハ・ラウンドに関する仕事を2年間経験した後パリで2006年から国際エネルギー機関(IEA)とOECDの事務局で勤務しました。結局IEAとOECDで計5年超いまして、その後、東京に戻り東大で働きはじめて今に至ります。
———IEAへは公募に応募されたそうですが、前々から「海外でやっていきたい」というご意思はあったのですか?
芳川:当時、経産省の人事当局から「応募してみないか」と声がかかりパリに試験を受けに行きました。2006年の初頭です。IEAのHead of Country Studies Divisionという日本で言う課長ポストですが、その面接と筆記試験を受けたら運よく受かって、それでIEAに2年弱いて、その後OECDに移りました。OECDの方はDeputy Directorポストで、勧められて受けてみたらうまくいきました。その後縁あって2010年にOECDからIEAに戻りました。確かに、若いときから国際的な仕事をしたいという希望を持って役所に入りましたが、具体的にこのような人生といいますか、ポストを経験することになるとは全く思っていませんでした。事前に自分がこうなると分かっていたら、若い時にもっと別の準備をしておいただろうとは思います。例えばフランス語を勉強するとか、国際機関へインターンに行ってみるとか。私はエネルギーやイノベーションのサブスタンスとともに、マネジメントも期待されていましたし、このようなことは何とかできるにしても、一定のテーマのもとで一からリサーチをしてレポートを仕上げるという経験を若いときにやっておいても良かったと思います。もっと引き出しを増やしておけば良かったということです。

国益と貢献 自分の付加価値はどこにあるのか
———グローバルな分野でご活躍されていますが、それができたご自身の適性は何だと思われますか?
芳川: 適性があったかどうかは分りません。ただ、これで生きるしかないとは思っていたと思います。そういう意味で一定の覚悟は持っていたように思います。国際的なことに限らないとも思いますが、自分はこの会議でどういう貢献ができるか、何が自分の付加価値なのかということと、国際交渉では国益ですよね、その双方をしっかり踏まえることが重要だと思います。国益はもちろんとして、会議のその場で自分がどういう貢献をすべきか、できるかをしっかり考えるということです。いつも思っていたのですが、国際会議に行くと日本の役人の多くは非常に能力の高いノートテイカーで、頭も整理されて問題意識も持っている。最近は上手な方もたくさんいますが、仮に英語は上手くなくても、分からないところは後で聞いて補足したり、ノートテイカーとしては非常に優れている。しかし多くの場合、本当に重要なことは、ノートテイクするというよりも、それに加えて自分が話して相手を説得すること、少なくとも相手にノートテイクさせること、最低限出席者に「日本がこう言っていた」とそれぞれの本国にしっかり報告させることが重要だと思うのです。他の出席者を説得し、彼らにノートを取らせるのが仕事で、自分が書くのは二の次という気が私はしていました。そのためには、確かにものすごく準備がいるし、あるいは、しっかりした理屈と洞察力のようなものがないといけないのですが、それが必ずしも十分ではないこともあるように思います。もっと正確に言うと、今は、これまでのように日本の力や勢いがあって何もしなくとも各国が日本に注目してくれているような環境ではなくなってきているので、その分、個々人の力と意識変化が必要になってきていると思います。留学後にイラン、ニューヨーク、ジュネーブ、パリに行った期間、国際社会における日本の力は、どんどん衰えてきているような気がしていました。
———日本の力はいつ頃がピークだったように思われますか?
芳川: 日本に対する世界の一般的な関心ということでみると、もっとも盛り上がったのは80年代後半くらいから90年代初めではないでしょうか。プラザ合意の直後、Japan as Number Oneのころで、私がちょうど留学に行った時期からイラン勤務をした時期くらいでしょうか。その後、ニューヨークに行った1990年代終わりごろにはもう中国も台頭しはじめていましたし、日本ではバブルもはじけていました。私がそれを本当に痛感したのは、ジュネーブでドーハ・ラウンドの交渉を担当したころですね。いろいろな交渉ごとをしているので折に触れて小さなグループで食事をしたり、フレンズと称して同じ立場の国と共同で論陣を張るためミーティングをしたりするのですが、その頃は80~90年代の経験から、例えば日本とASEANとの関係では日本の主張には一定の重みがあるのではないか、全部ではなくともある程度は日本の話を聞いてくれるはずだ、という気持ちでいました。でも、現実は国際環境もASEANの実力も変わっていて、当然ではありますが、日本が当時思っていたほどにはASEANも日本に同調するわけではありませんでした。ASEANがいろいろな意味で成長したということでもありそれはいいことなのですが、日本としてはなかなか寂しいと思うこともありました。
———今後、日本の存在感は上向くことはあるでしょうか?そのためにGSDMは始まったのかもしれませんが。
芳川: 上向いてほしいですね。国の力とともに国際プレゼンスも一緒に衰えてきているように思えますし、こっちはもっと加速度的に下降しているような気すらします。だから、ヒューマンな要素というか、個々の日本人の実力・人間力というか、人材の力で少なくともある程度の部分は補えるだろうと思います。ヨーロッパの歴史などを振り返ると過去に国力は衰えたけれども、それをゆっくりにしたり、経済以外の面で存在感を示したり、いろいろな国の例がたくさんあるわけですから。そういう面でもこのGSDMは貢献できるはずだと期待しています。

曖昧ではなく明確に相手を説得するコミュニケーションスキル
芳川: 日本の社会に居ると、私もそうなのですが、日本語で話しているときに「あれだよ、あれ」といい、相手も「うん、あれだ」といった形で会話が進み終わってしまうことがあります。会議ではさすがにあまりないのかもしれませんが。でも、英語でしっかり議論して、かつその議論の仕方も「あれ」とかじゃなくてエビデンス・ベースで、メソドロジーもしっかりしている、いわゆるユニバーサルな言語とグローバルなメソッドで議論できるということが大事だと思います。アカデミックなバックグラウンドもあるとなおいいです。そういう意味でインターナショナルな言葉で明確にちゃんと説得できる力が大事ですし、それができる人が必要だと思います。
———単なる語学の問題だけじゃなくて。データとロジックがあるということですか。
芳川: そうです。それがあると全然違うと思います。ディベートのスキルの問題でもなくて、仮にそういうものが何にもなくて、たどたどしい英語でも、ちゃんと人を説得することが必要だと思いますし、それをやるのが結構難しいと思います。だから、その基礎をちゃんと学んでもらいたいです。私の立場からGSDMの学生にもよく言ったりするのですが、当該研究は社会とどういうインタラクションがあって、具体的にどんな役に立つものなのか、そういったベースの上に目標設定ができないといけないと。理科系の学生にとっても、こういう社会との繋がりなどをちゃんと考えることがグローバルリーダーの条件の一つではないかと思います。単に英語が上手だとか、ディベートがうまいとかにとどまらず、WTOの交渉やOECDやIEAで、日本人でも外国人でも本当の意味で実力のある人と一緒に仕事をしてきた経験を踏まえると、たしかに天性のもの、たとえば自分の腕一本でのし上がっていくバイタリティとか、本当に覚悟が違う人はいて、こういうものをGSDMでつくり出すことは難しいかもしれませんが、この思考や行動の基礎、マインドセットぐらいは何か伝えられるのではないかと思いますし、むしろ、そういうことが大切だと思います。