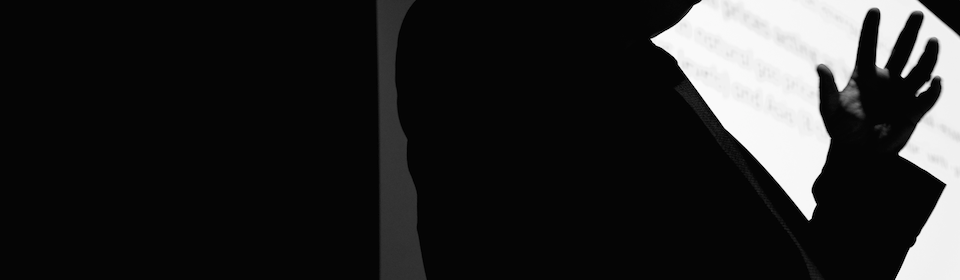資源を中心に 新しい社会の枠組みをつくる
東京大学東洋文化研究所 新世代アジア研究部門 教授 佐藤仁
資源を中心に置いた新しい枠組みを

———佐藤先生は資源がご専門で、かつ歴史的なアプローチも取られていらっしゃいますが、どういった関心をお持ちなのでしょう?
佐藤:僕は「人間社会における豊かさとか貧しさ」というところに究極の関心があるんです。それを促し媒介してるのが資源だと思っていて。例えば資源があってもアクセスできないとか、あるいはあったのに誰かに奪われた、ないと思っていたものが見つかった、人間の協力と非協力、科学的な発見など、いろんな要素によって伸びたり縮んだりするものが資源なんだと思います。資源が環境保全の観点からも人間の生活の向上という観点からも、一番真ん中にあるというふうに思っているんです。
開発と環境のジレンマみたいな話もありますが、資源はその真ん中に横たわっている共通項なので、むしろこの使い方が偏っていると環境問題も起こるし貧困も起こると考えて、資源を中心に置いた何か新しい枠組みを組み立てたいと思って考えていました。そしたら既にそのことを考えていた日本人が過去に何人もいるということが分かってきたんです。
———それでインタビューをなさっていたわけですね。資料は残っても、それに至った生の声や当時を知る方を探すのは年々難しくなっていきますよね。
佐藤:昔の人って、いろいろ書き留めている場合が多いんですよね。それは家や倉庫の奥にあったりして、その人が亡くなると全部処分されちゃうんです。でも残すべきは、その人の頭の中にあるものプラス、その人が書き残したメモや集めたりしたものの一群のセットなんですけど、その価値が周りの親族には分からないことも多いんですよね。「あー、お父さん、また変なこと書いてるよ」みたいな。
でも僕、自分では歴史的アプローチというスタイルを取ってるつもりは全然ないんですよ。政策というのは「分かっているのにできない」ことが多いんですが、分かっていたのにできなかったというのは、つまり政策提言した時に何らかの理由と原因があって、そのために政策が生かされなかった可能性が高いことを意味しているわけです。だとすると、どうして知ってることが生かされない仕組みができたのか、その仕組みを誰がいつ作ったのか、代替案はなかったのかなど、その仕組みの前提が作られてきた経緯を調べてみないと、本当に意味のある政策はできないとだんだん思うようになったんです。だから僕にとっては至極正道なんだけど、周りを見てみたら似たような人があまりいなかったという感じで。
あとは自分の性格もありますね。例えば「資源」という言葉とかも、一体、日本人がいつ頃からこの言葉を使い始めたのか大本を辿りたくなるんですよ。その辺りは、僕は魂がちょっと歴史的な人間なのかもしれませんね。

———特に最近、力を入れて取り組んでいらっしゃることは?
佐藤:世界における開発と環境の問題をどう考えるかということを本に書きたいと思っています。あと、もう少し研究的なことで言うなら、東南アジアのいろんな国が資源とか環境を統治するために行政制度をそれぞれ発達させてきたわけですが、例えばある国は水をまず管理して次に森林、次に鉱物、大気という順序だけど、他の国はまた順序が違うこととか、それが起こした地域の人々との軋轢とか。あとは、その軋轢が解消されていったメカニズムが国や地域によってどう違うのかとかを考えていますね。もう一つは研究成果の出し方として、専門的なものはすべて英語で書くと割り切って英語の本を書きたいと思っているのと、それとは別に今まで自分がやってきたことを分かりやすくまとめた新書も今年の夏頃を目処に出したいと思っています。
あとは、資源ガバナンスの比較研究みたいなのをやりたいと思っているんですが、これもやっている人が全然いないんですよ。これは歴史的には植民地時代ですね。アジアの場合、ほとんどのシステムは植民地時代に作られているので。どの国がそこを治めていたかとかによって、相当スタートが違うわけです。資源の分野というのは大抵一国一資源なので、私はタイの森林をやっていますとか、インドネシアの水をやっていますという人はいるんですけど比較研究をやってる人は殆どいないですね。全部を、しかも並べてどういうふうな配置になっているかをやりますなんていうのは、お前ふざけるなって、多分言われると思います(笑)。
社会科学の醍醐味は全体像を示すこと
———GSDMでは技術を知った公共政策が分かる人、公共政策の分かる技術者を育てようとしていますが、佐藤先生のようなアプローチを身に付けるのは今の学生にはとても大変なのではないですか?
佐藤:僕はどうにか食ってこれていて、これはすごく幸運だったというのはあると思うんです。でも、何ていうのか、こういうことをやる人って何人もいらないと思うんですよね。みんながみんな、つまり大量生産に向く話じゃないんですよ。だから本当に何か10人の中の1人とか0.5人ぐらいがいればいいんだと思うんです。
ただ、社会科学にとって決定的に重要だと思うのは、全体像を示すことなんですね。パーツを詳しく調べるというよりは、「全体像はこういうふうになっていますよ」と示すところに社会科学の醍醐味があるというか。あるいは、いろんな転換点やここが転換点ですって示すこととか、そこに一番社会的に重要な機能があると思うんですよ。でも、みんながみんなそうなったらいいのかといえば、みんなに向いている話でもないわけで。だから、そういう人たちがGSDMで出てくるようになればいいですよね。でもこれは訓練でそうなるのかというのはちょっと分からないですね。そういう素質がないのに無理やり頭をトンカチでたたいて、「お前、全体像を見ろ」っていうのはちょっと。

———先生はアメリカのプリンストン大学でも授業をされているということですが、言語の違いはもちろんですが、講義内容や雰囲気など、それ以外の違いはありますか?
佐藤:そうですね、全体的に授業の重みというか、1つの授業に掛けるエネルギーは、学生も先生も向こうのほうが大きいんですよね。要するに、例えば1つの授業で標準的に読んでくることが期待される文献の量っていうのが圧倒的に多いので、それに対する学生評価というのもかなりシビアなものがありますね。プリンストンの場合、学部生が年間500万とか600万円払って、それで院生が負担少なく在籍できてるという側面があるので、学部生の満足度ってすごく大事なんですよ。学部生が喜ぶ授業をいかにオファーするかというのを大学としても非常に気にしています。先生たちは本質的には研究、リサーチのほうに関心があるんだけど、かといってティーチングもまったく手が抜けないという状況なので鍛えられますね。
前回はプリンストンのEast Asian Studiesというところで授業を開講したんですけど、今度は初めてWoodrow Wilson Schoolという公共政策大学院でやらないかというお話をいただいて、それも初めてやるんですね。そこで学生の評判もいいよ、またおいでって言われれば大学が許してくれる限りはまた行きたいですが、お前もう来なくていいよって言われたらもうそれまでです。東大でもティーチングアワードみたいな、学生評価がすごく良かった先生にボーナスを出すとか、やってもいいですよね。僕は羊羹でも、どら焼きでもいいんだけど。(笑)
※参考リンク
- 佐藤仁先生著 「持たざる国」の資源論
http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/news/pub110704.html