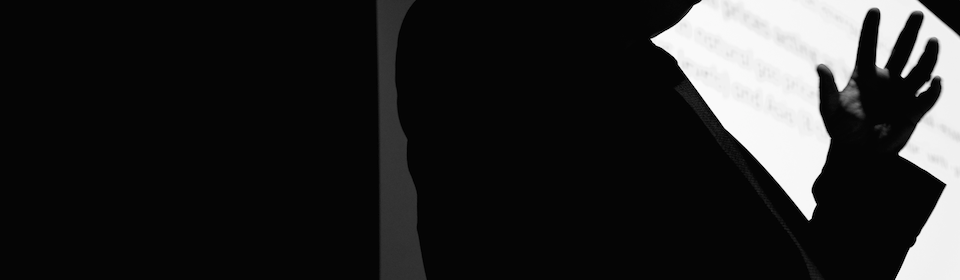医療の課題を解決する「仕組み」をつくる
東京大学大学院医学系研究科教授 小林廉毅

医療の仕組みづくりを研究したい
———小林先生が公衆衛生の研究に関心を持たれたきっかけは何ですか?
小林:医学部入学後、色々な本を読んで思ったのが、医療問題の解決には技術の高さ、つまり医療が進歩していくことが一つ。もう一つは病気の人や困っている人に、どこまで必要な医療技術を届けられるかなんだと考えるようになって、そこが制度としても研究としても弱いんじゃないかと思ったんです。僕は旅行が好きで医学部の学生のときに日本の各地を回って、僻地医療について考えました。一番に思ったのは、「なぜ僻地医療という問題があるのか」ということ。やはり仕組みがないといけないし、仕組みがあったとしても、それを改善していかなければいけないんだと。卒業したら日本の地方に行こうと思い、沖縄県に行きました。沖縄県に行ってみると、離島が多いので、むしろ、「仕組み」がきちんとできているんです。やはり仕組みづくりが大事だと思いました。 以前から公衆衛生に関心はありましたが、僕が学生の時の公衆衛生は産業保健が中心でした。しかし、僕は予防も含めた広い意味での医療の仕組みづくりの研究がしたいと思ったんです。当時、アメリカでそういう研究が結構進んでいたので、そのようなことをやっていこうと思いました。 帝京大学の公衆衛生学教室に助手として入った時、その教室が医療活動にも熱心で在宅医療の研究だけでなく実践もやっていたんです。長野県では、行政と協力して在宅の高齢者の訪問をしていたので、その活動に参加し、一緒に研究もしました。これはすごくラッキーでした。僕の学位論文は終末期医療、特に在宅を熱心にやっている自治体と協力してやった研究で、がんあるいは脳卒中で入院されている方と在宅の方との医療費比較をしたんです。
———技術だけではなくパブリックポリシーが必要だという考えはGSDMが強調していることですね。先生は経済学のアプローチを研究に取り入れられていますが、当時かなり先駆的だったのでは?
小林:学生の時から制度絡みのことに関心があったのですが、医学部の中で経済学を教えてくださる先生はいなかったですね。経済学の教養書みたいなものを学生のときに読んだくらいだったので。帝京大学で助手を4年ぐらいしたところで、アメリカのハーバード大学に1年間研究留学しました。その際に、経済学をきちんと勉強したいと思ったので、ハーバード大学のケネディ・スクール(公共政策大学院)で公共経済学の授業を2つ聴講させてもらいました。その授業がすごく分かりやすい授業で、それが経済学を理解するのに非常に役に立ちましたね。ただ、耳学問だとなかなか使いこなせないので、帰国後、実証データを使った研究で実践を学びました。当時書いた論文自体はそんなに高等なテクニックは使わず、経済学の基本的な考え方を医療の分野に応用したものでしたが、当時そういう研究は少なかったので、オリジナリティがあるということで雑誌の反応はよかったと思います。ただ、社会の反応はまた別です。その研究を専門する人の数と、それを理解する人のマスが増えてこないと、なかなか学問分野として受け入れられないので。

———そのような学際的な取り組みは、今は定着してきたのでしょうか?
小林:関心を持つ人は非常に増えたと思います。あの当時、もう1つの大きな問題は日本国内でデータがあまりも使えなかったことだったんです。アメリカに比べると、本当に少ない。レセプトも紙媒体しかなく、そもそも協力してくれる自治体もない。協力してくれるところを探して、やっと了承してくれた自治体でも、レセプトは紙媒体なので、データを一から入力し直さないといけなかったんです。 しかし、時代は変わりました。今はむしろ国が主導してレセプトを電子化して、研究者に提供する体制を作りつつあります。まだまだ制限は多いですけど、そういう道筋がついたので、以前とは状況がだいぶ違うと思います。アメリカは1980年代からメディケア(高齢者等を対象にした公的医療保険制度)のレセプトデータが使えるようになっていますので、アメリカに比べるとまだまだ不十分ですけど、でも確実に使えるようになっているというのが大きいですね。
———レセプトの分析がしやすくなった背景には何か後押しがあったのですか?研究者の声とか?
小林:もちろん研究者の声もあるし、あとは小泉内閣の時に政治主導で一気に進みました。5年計画で進みました。もともと臨床ではデータの重要性はかなり認識されていて、例えば、昔から薬は臨床試験でデータを集めないと薬の申請自体ができなかった訳です。そのようにデータは大事だという前提があって、その上で新薬だけじゃなく、医療行為一般についてもデータを集めてきちんと分析して効果判定をし、それに基づいて治療を決めていこうという流れが欧米を中心に90年代に広がっていました。それが、EBM(Evidence-Based Medicine)です。その後、政策の方向性も変わってきました。
———EBMが出るまでは、エビデンス・ベースドではなかったのですか?
小林:いいえ、当時もちゃんとエビデンスはありました。ただ、エビデンスの考え方が今と違ったんです。それまでのエビデンスは、専門家の「これがよい」という判断のことを意味してました。あるいは一つの研究だけで決めたりしていた。でも、一つの研究だと、それが良いか悪いか判断がつかないですよね。研究が積み重なってやっと正しいものがはっきりしてくるので、追試が行われないといけないんです。 つまり、一つ一つの研究はもちろん重要だけど、ある程度それがマスにならないと、実際に人に対して自信を持って使えるものにはならないんです。積み重ねです。この辺りが、実際に人を対象にする研究と基礎研究の違いだと思います。基礎研究は直接人に使いませんから、1個すごい発見が出れば諸手を挙げて喜びますが、臨床や公衆衛生は直接人にかかわるものなので、1個の研究で物事を決めるというのはリスクが大きすぎます。積み重ねがないといけません。それには当然時間もかかります。
時代と場所で「パブリック・ヘルス」の意味するものは異なる
———先生は公共健康医学がご専門ですが、パブリック・ヘルスを「公衆」と訳すか、「公共」とするか、何か違いはありますか?
小林:公衆衛生という言葉は憲法にあるので、それはそれで歴史的に非常に重要な言葉です。ただ公衆はちょっと古い言葉というイメージがあったりします。でも憲法で使われているので、それは一つのよりどころでもあるんです。 パブリック・ヘルスは、時代と場所でその意味するところが全く違います。例えば、今でも途上国ではそうだと思いますけれども、上下水道をきちんと整備して、ごみをきちんと処理すれば、それだけでも人々の健康状態は上がります。あと、栄養状態や食糧事情とか。でも、今の日本ではそういう話はあてはまりません。つまり現実から始まる話なので、そこは臨床医学と一緒です。ただ、臨床は患者一人一人を対象にしますが、公衆衛生は集団、たとえば現代の日本人、あるいはシエラレオネの人々というふうに集団を対象にします。相手と場所、時間によって事情が異なってきます。まずは集団の健康状態を把握することが基本なので、それは疫学の独壇場となります。パブリック・ヘルスをやるんだったら、疫学の基本はなるべくマスターしてほしいと思います。

———公衆衛生をこれから勉強していく学生に持って欲しい問題意識などありますか?
小林:難しい質問ですが、やはり本人のプリファレンス(やりたいこと)が大事なので、適性と本人の関心に従ってやっていけば自然とその先はつながって行くと思います。今、東大の公共健康医学専攻は医学部出身者が多いですけれども、世界的に見ると、例えばハーバードの公衆衛生大学院では経済学や工学、政治学の出身者が多いんです。なので、別に医学をバックグラウンドにしていなくても、まずは仕組み、制度論から入る人がいてもいいし、入り口はどこからでもいいと思います。公共政策や公衆衛生は学際分野ですので、入り口はどこにでも開いています。GSDMのようなバーチャルな分野横断型の仕組みがあるのは、「入り口」としてはいいかもしれないと思います。
———人間の行動や社会制度にもかかわる公衆衛生学ですが、今後、どのような人材育成が必要でしょうか?
小林:この分野は近年、非常に多様化、複雑化しているので、たとえば大学院生でも学部生でも社会に出て一定期間置いて、また大学や研究機関に戻って充電する期間をもつということを制度化するといいと思います。いわゆるリフレッシュ教育ですね。現状、東大の公共健康医学専攻はまさにそういう役割も一部担っていて、入学者の3~5割は職歴が数年あるいは10年以上の人たちです。 実際、そういう人たちが学びやすいようなカリキュラムの1年で修了できるコースを用意していますが、それが機能しています。社会人経験者から実社会の生の情報が入ってきますし、若い学生も刺激を受けています。また、新卒者の方も、最新の統計やコンピュータの扱い方を年配者にアドバイスしています。 新卒者と社会人経験者がお互いが助け合えて学び合えるような仕組みを、今後、大学は提供していく必要があると思います。基礎科学だと難しいかもしれませんが、現場に近い分野、たとえば経済学や公衆衛生学などはいいと思います。イノベーティブな教育の仕組み作りは、今後どんな領域でも重要になってくると思います。