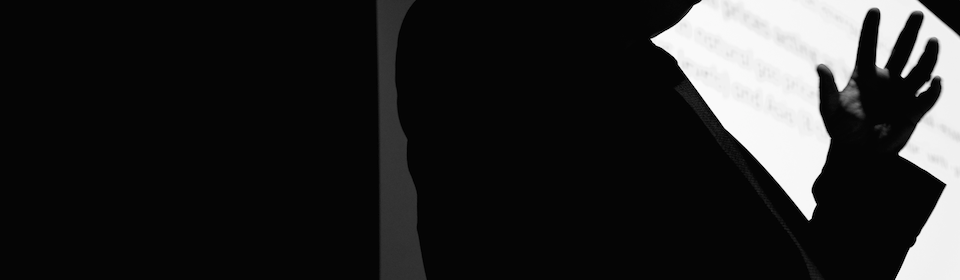セイフティとセキュリティをリスク概念で可視化する
東京大学公共政策大学院特任教授 岸本充生

———セイフティとセキュリティ、そしてリスクはどういう関係にあるのですか?
岸本: セキュリティ(安全保障)が主に扱うのは、犯罪やテロのような意図的なものや悪意のあるものです。セイフティ(安全)は非意図的あるいは非人為的なもので、発生源がヒューマンエラーとかを含めた事故や人間の意図の及ばないような自然現象などです。分かりやすく言うと、飲料水に化学物質を意図して混ぜたらセキュリティ問題だけど、汚染物として入ってしまったらセイフティ問題です。語源はともにラテン語で、セキュリティは不安がないこと、セイフティは負傷がないことです。つまり前者は主観的、後者はより客観的なのです。
リスクというのは、セイフティとセキュリティの両方に適用できる概念です。セイフティもセキュリティもともに、リスクという概念をかまさないと定量的に扱うことができません。
セイフティの場合は、リスク概念を使って定量的に扱う「リスク評価」が1970年代くらいから欧米で始まり、日本でもいくつかの分野では近年ずいぶん進んできました。セキュリティは人間の意思がからむため、発生確率の推定は主観的にならざるを得ず、定量的に扱うことがとにかく難しいために、これまであまりリスク文脈で語られてこなかったのです。
セイフティとセキュリティのままでいたら、ゼロかイチの話になってしまうので、すべての側面でリスクとしての議論ができるような土壌を作っていきたいのです。
———セキュリティ文脈でも政策の優先順位を議論するときにリスクの大きさで考える必要があるということですか?
岸本: そうですね。たとえば、近隣の国からミサイルが飛んでくるというセキュリティ問題と尖閣諸島で事が起こるというセキュリティ問題の、どっちに資源、リソースを投入すべきか。それを比べる手立てがこれまでありませんでした。それをエビデンスベースで意思決定できる形にもっていく、あるいはセキュリティ政策の根拠を説明するためには、リスクとして検討する必要があります。セキュリティ分野にリスク概念を入れていくとはそういう意味です。
———日本でリスク概念を活用した議論がされてこなかった理由は?
岸本: そもそも安全をどうとらえるかというカルチャーの面に関わると思います。これまで日本人は安全を「結果」で判断してきたのです。30年間無事故だったから安全だというような「神話」です。明日事故が起こるかもしれないのに。福島第一原発ではそれが神話にすぎないことが明らかになりました。
でも安全は、手続きやプロセスでしか確保できないというのが国際的なコンセンサスですし、そうじゃないと新しいものの安全が定義できません。つまり、安全を結果じゃなくてプロセスで判断するように、考え方とかカルチャーを変えないといけないわけです。この点で特に問題が生じているのは新規技術に関してです。100%の安全を証明できるまでは新しい技術が導入できないということになりかねません。そのためにイノベーションが止まっている例がいくつもあります。ロボットとか、ナノマテリアルなどの新素材とか。結局、結果でしか安全を評価できない社会には新しいものはとても入りにくい。

———安全の定義を間違うと社会にイノベーションが起こらないということですね。
岸本: はい、たくさん事例があります。たとえばお掃除ロボットは日本でもたくさん売れています。2年前に産経新聞のウェブの記事に、ある企業の話が載っていました。早くから技術は開発されていたのだけれど100%安全が保障されなかったので商品化を見送ったという主旨でした。読んで驚いたのが、社内で商品開発について検討された時の話です。仏壇にぶつかって、ろうそくが倒れて火事になったらどうするとか、階段から落ちてその下に赤ちゃんがいたらどうするだとか。延々話し合って、結局発売を見送ったというのです。僕はこういうケースを「何かあったらどうするんだ症候群」と呼んでいるのですが、こうした土壌で果たして日本にイノベーションを起こせるのだろうかと疑問に思います。
———日本の社会はいつから、どうしてそうなったのでしょう?
岸本: 安全に対する価値観が180度変わったにもかかわらず、行政や事業者も含めた社会がその変化についていけてないのだと思います。今からおよそ100年前、社会に自動車が初めて導入された際には、交通事故で毎年ある程度の死傷者が出ることが予想されたとしてもそれが技術導入を妨げることにはなりませんでした。分からないものはとりあえず安全と仮定して、何か不具合が起きてから対処するという文化でした。実際、フロントガラスに頭突っ込むことが多いことが分かってからシートベルトしましょうとなり、子供の負傷が多いことからチャイルドシートに座らせましょうとなったわけです。実際の事故データに基づいて改良されてきたわけです。変化の兆しが見えたのはおそらく70~80年代あたりだと思います。そして21世紀には180度変わってしまいました。すなわち、分からないものはとりあえず危険だと見なされるようになりました。
思考実験でよくやるのですが、今、誰も自動車のことを知らないと仮定して、ある会社が「car」という製品を発明したとします。「すごく便利です。好きなところへ好きな時に行けます。ただし国内で年間4000人くらい死にますけどね」といったら、社会は受け入れないでしょう。これが180度変わった帰結の1つです。

安全であることを事前に証明しないと社会が受け入れないというカルチャーになったときに、新規技術や新規材料の「安全」を証明するということはどういうことなのでしょうか。100%安全を証明するというのはいわゆる「悪魔の証明」というもので不可能ですが、許容できないリスクがないことを証明することならできます。それをまず、行政や事業者が実践していくということじゃないかと思います。
———でも消費者にとって「許容可能なリスク」は、ある意味で存在しないのでは?
岸本: そうですね。何をもって「許容できる/できない」とみなすかというのは、人によって違いますし、時代によっても、状況によっても違います。だから本当はこれを社会で決めていかないといけないと思うのです。つまり、これを安全目標と呼んでいますが、たとえば発がん性の化学物質だったら、生涯摂取し続けることで10万人に1人がそのがんで死ぬという濃度レベルを安全目標にしています。河川堤防は200年に1回、あるいは100年に1回ぐらいは洪水になるかもしれないが、それ以外は堤防で防ぐことができるというのを堤防の安全目標にしています。これまで日本では、こういったことを専門家に任せてしまって、社会で議論をするということをしてきませんでした。そのためには、複数の代替案を提示し、それぞれの利害得失(リスク、コスト、ベネフィット)を予測し、それらに基づいて、多様なステークホルダー参加のもとで議論し、合意形成を図るという手続きを確立する必要があります。これが、安全に対する価値観が180度変わってしまった社会における安全の作法です。
(インタビュー 藤田正美、記事構成 柴田祐子)